| ●3ポイント式主鏡セル |
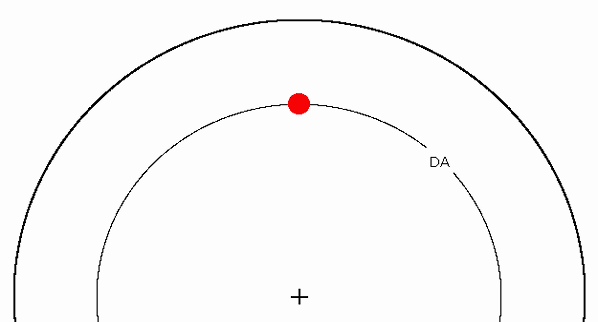 |
| 主鏡直径をDとした場合、 DA=0.7D 直径DA上に120度間隔の3カ所のパッド(赤丸)で保持する。 30Cm以下の、1/10厚以上の鏡なら3ポイントで大丈夫だと思います。 |
望遠鏡自作データ集
| 主に眼視用のニュートン反射を自作するときに必要と思われるデーターを集めてみました。良かったら参考にしてみてください。 |
| ●有効最低倍率の求め方 |
| 主鏡の有効径をD、瞳径をEとした場合、 有効最低倍率=D/E で求められます。また、このときの接眼レンズの焦点距離は、F=口径比とした場合、 接眼レンズの焦点距離=F×E F4.5の望遠鏡で瞳径7mmで使用したい場合は、4.5×7で、31.5mmくらいのアイピースが必要なことがわかります。なお、一般的には最大瞳径を7mmとして考えますが、個人差がありますので、測定器などで測ってみるのもいいかもしれません。すこしづつ間隔の違う2個の小穴を幾組かあけた板を目の前に置き、向こうがまったく見えなくなる小穴の間隔がその時の瞳径です。 |
| ●実視野と倍率と見かけ視野 |
| 見えている実視野と倍率と接眼レンズの見かけ視野の関係は、 実視野=見かけ視野/倍率 倍 率=見かけ視野/実視野 見かけ視野=実視野×倍率 |
| ●3ポイント式主鏡セル |
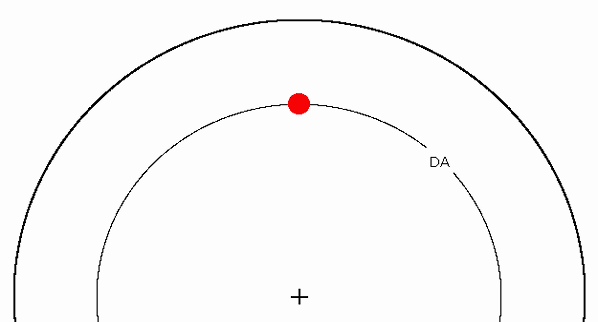 |
| 主鏡直径をDとした場合、 DA=0.7D 直径DA上に120度間隔の3カ所のパッド(赤丸)で保持する。 30Cm以下の、1/10厚以上の鏡なら3ポイントで大丈夫だと思います。 |
| ●9ポイント式主鏡セル |
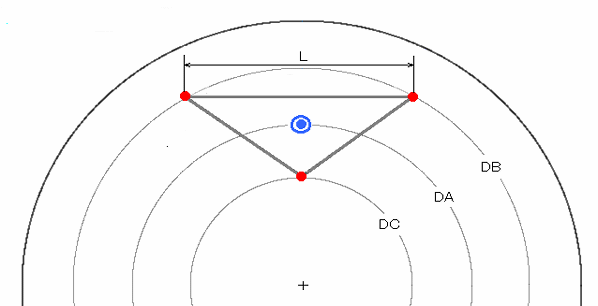 |
| 主鏡直径をDとした場合、 DB=0.816D DA=0.612D DC=0.408D L=DC 直径DA上の120間隔の3カ所に設けた3角板の3点パッド(赤丸)で保持する。 3角板の中心(青丸)は 少し首を振るように作ります。3角板が回転しないようにするためには、ドーナツ状の薄板でDCライン上の3点を繋いでしまうと良いです。 35Cmを越えるものや、20Cmくらいでも惑星用などの高倍率を使うものには有効だと思います。 |
| ●18ポイント式主鏡セル |
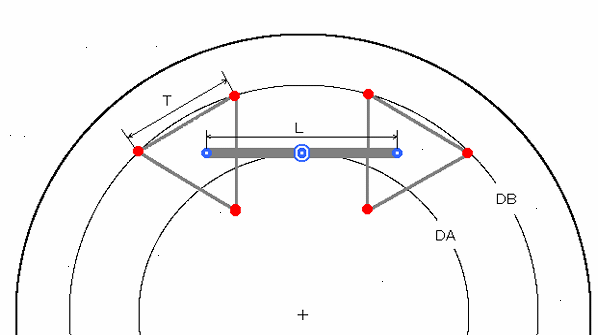 |
| 主鏡直径をDとした場合、 DA=0.576D DB=0.816D T=0.211D・・・・・(3辺同じ長さの正3角形、赤丸はパッド位置) L=0.333D 直径DA上に120間隔で3×2カ所設けた3角板で保持する。それぞれの支点(青丸)は少し首を振るように作りますが、シーソーを上から見た状態のように作るのが楽です。 50Cm超級や、シンミラー(極薄ミラー)などでよく使われます。 |
| ●斜鏡短径の求め方 | |
| 最小斜鏡短径は、斜鏡から焦点位置までの距離をL、主鏡口径と焦点距離の比をFとすると、 L÷F で求められます。 ただし、これではまったく余裕がありませんから、本来は必要とする視直径θを決めて (焦点距離−L)tanθ で計算した値を加えます。 ところが最近の短焦点鏡にこの式を当てはめると、斜鏡が巨大になりすぎてしまいます。実際には眼視用の場合周辺減光があっても分かりませんし、斜鏡が大きいのは百害あって一利無しですから焦点面のどの程度の範囲にフルに光が来るかをもとに斜鏡短径を決めるのがよいと思います。 主鏡焦点面の直径dmmの範囲に100%光量が来るようにするには、 斜鏡短径=L/(焦点距離/(D−d))+d となり、 たとえば、口径200mm、焦点距離1000mm、L=225で直径15mmの範囲に100%光量が欲しい望遠鏡の場合、 225÷(1000÷(200−15))+15=約56.6mm となります。 個人的には比較的低倍率で広視野が欲しい星雲星団用にはd=10〜15mmくらい、高倍率中心の惑星用にはd=5〜10mmくらいがいいかなと思っています。斜鏡面の端はダレていたりすることが多いので、あんまりぎりぎりにするのは考えものだと思います。 |
| ●斜鏡のオフセット量 |
| 口径比の小さい望遠鏡でなるべく小さい斜鏡にするためには、斜鏡の中心点を主鏡光軸からオフセットした方がよいと思います。理由は光路図を書いてみれば簡単に分かると思います。 オフセット量はF=口径比とした場合、 斜鏡オフセット量=斜鏡短径÷(4×F)注:主鏡光軸に対するオフセット量です 斜鏡面は45度に傾けられているので、この数値にルート2(1.4142)をかけた値分、斜鏡中心から接眼筒側にオフセットしたところにマークを付けます。 たとえば、斜鏡短径90mm、F=4.5の場合、 90÷(4×4.5)=90÷18=5 となり、 斜鏡中心より5×1.4142=約7mm接眼筒側にマークを付けます。 あらかじめ斜鏡面の型紙を作っておいて、所定の位置に2mmくらいの穴をあけ、フェルトペンでマークを付ける方法が良いと思います。 |
| ●筒外焦点について |
| 眼視用の場合、接眼筒をもっとも縮めた状態で、アイピースアダプターから2Cm〜3Cm焦点位置が出るくらいにすれば、ほとんどのアイピースで合焦します。ただし、特殊なアクセサリーを使いたい場合は、そのアクセサリーに必要な光路長を調べて付け加える必要があります。 筒外焦点=最小接眼筒長+2〜3Cm アイピースアダプターなどを使う場合はその寸法も考慮に入れます。 |
| ◇参考図書 |
| ●反射望遠鏡の作り方:星野次郎著(旧版:紺表紙) 小学校4年の時にこの本を図書館で発見し、自作望遠鏡の趣味にはまるきっかけになった、私にとって記念すべき一冊です。私はP105の13Cm卓上型反射望遠鏡がとくに好きでした。ミラーの研磨からマウンティングまで、全般に渡って解説されていますが、とくにマウンティングが詳しく、多くの作例と共に詳説されています。 ●反射望遠鏡の作り方:星野次郎著(薄茶表紙) 上記本の新版です。大幅に内容が書き換えられていて、より多くの反射光学系についての作例が掲載されています。P183にFRP鏡筒についてふれてあり、これがきっかけの一つになってFRP屋になりました(^^;。 ●新版反射望遠鏡の作り方:木辺成麿著 ミラーの研磨に大変詳しく、鏡を磨いてやろうという人には必須本。私もこれを見ながら6年生の時15Cm鏡を磨きました。全然ダメミラーでしたが(^^;。中学の時に16Cm鏡を磨き始め、中ズリで高校受験のため休憩に入ったまま現在に至っております゜゜(o )☆\(--;)バキ ●15Cm反射望遠鏡の作り方:川村幹夫著 川崎天文同好会の川村さんの書かれた本で、天文ガイドに連載されたものに一部追加して発行された物です。大変実践的な内容で、厚いスパイダーの悪影響などについても一部ふれられています。 ●天体望遠鏡製作ハンドブック:川村幹夫著 材料に関する知識などについて詳しく述べられています。小口径屈折の製作では絞り環(遮光板)についての記述があります。 ●写真で見る自作天体望遠鏡:天文ガイド編 小さい本ですが、そうそうたるメンバーの自作望遠鏡が載っています。特に宮本氏のシーフシュピグラーには注目。 |
| 私の持っている本で参考になりそうなものを上げてみました。他にもいろいろあるのですが、内容的に大変怪しかったりするので省きました(^^;。全部絶版だと思いますが、古本屋めぐりをして探してみてください。 |